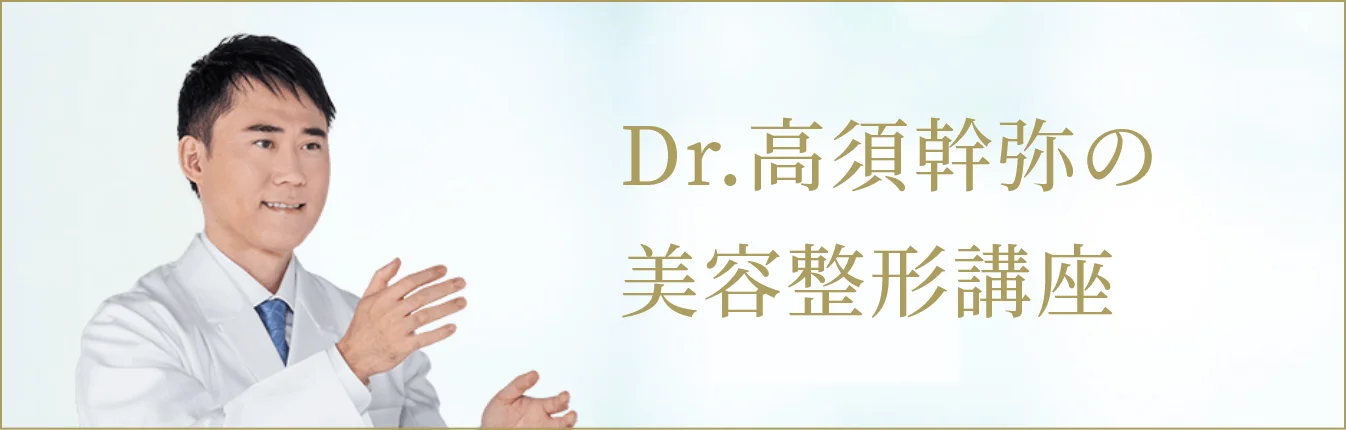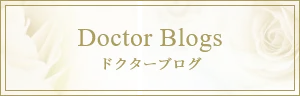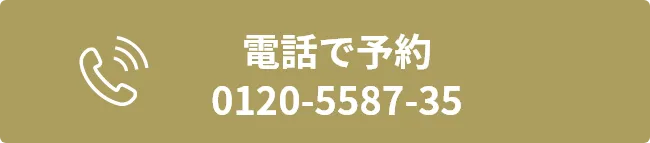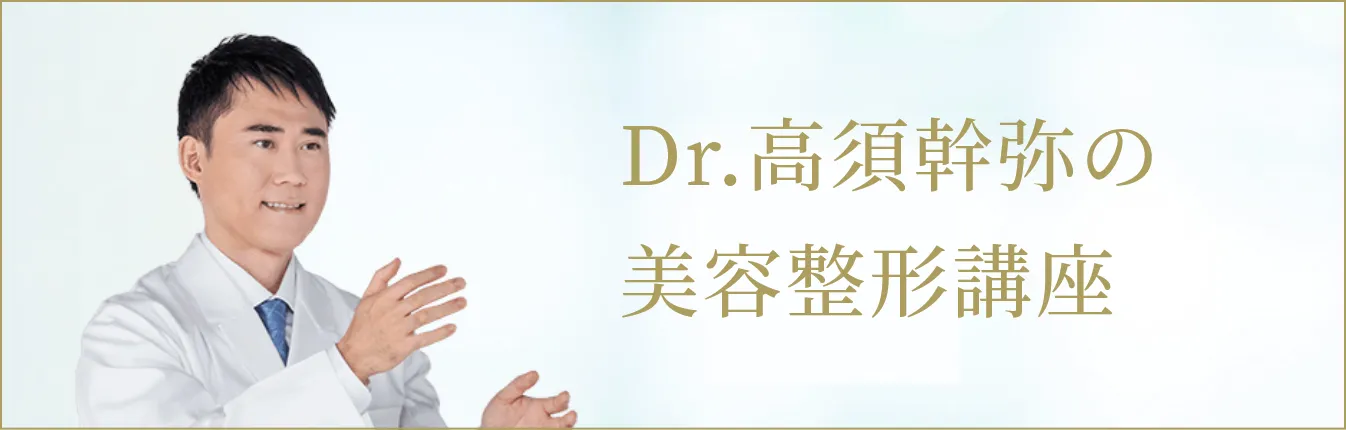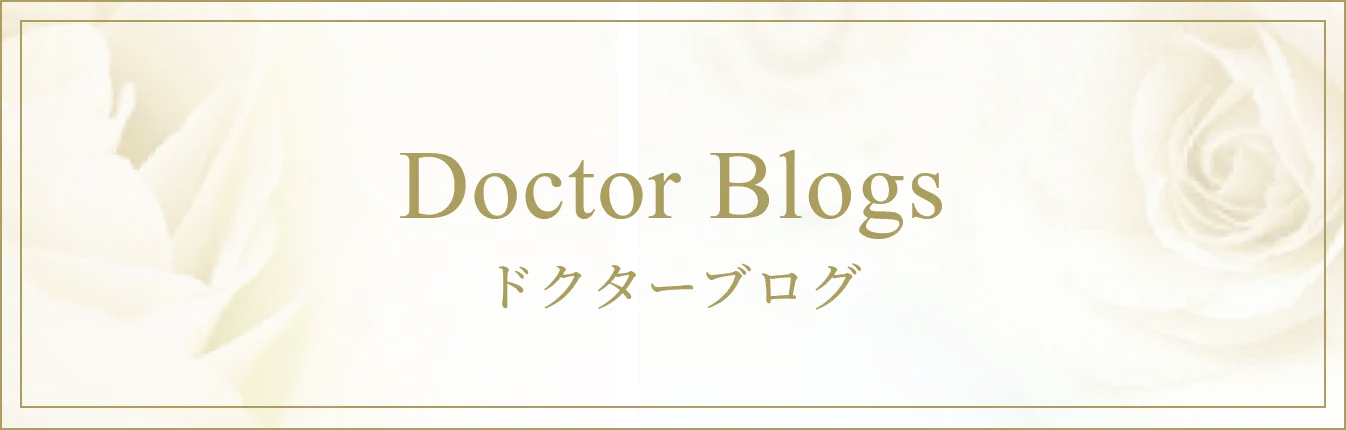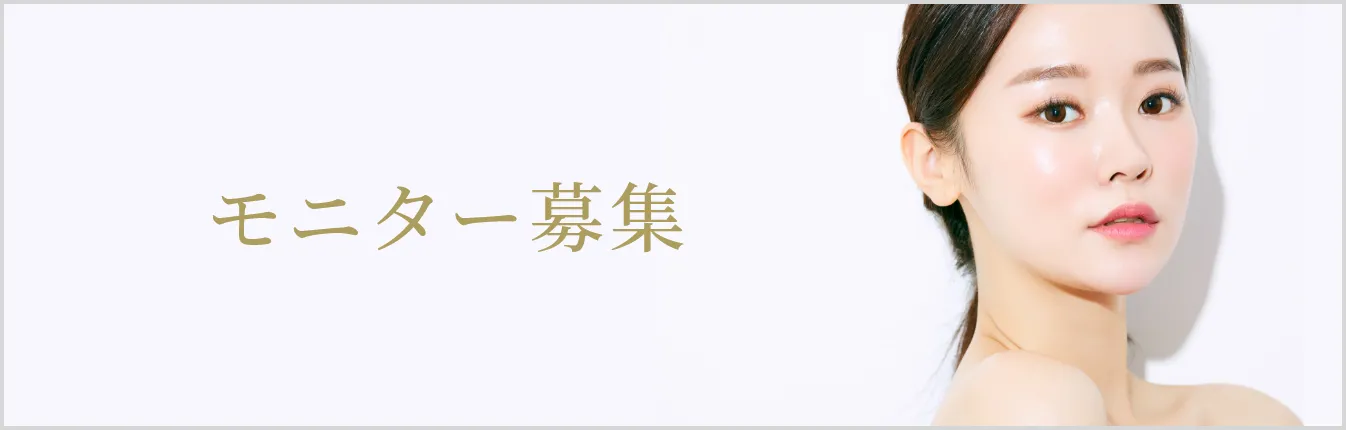- 高須クリニックホーム
- yes! 高須ビューティーナビ
- ビューティナビ記事一覧
- 粉瘤(アテローム)
- 粉瘤ができやすい人の特徴・傾向を医師がわかりやすく解説!
粉瘤ができやすい人の特徴・傾向を医師がわかりやすく解説!

2024.09.05
読了目安:この記事は約 11 分で読むことができます。
最近、顔や体に小さなしこりのようなものを見つけてなかなか治らないといったことはありませんか?
もしかするとそれは「粉瘤(ふんりゅう)」と呼ばれるものかもしれません。
粉瘤は、ニキビなどと間違いやすいこともありますが、自然には治らない良性の腫瘍のため過度な心配はいりません。
しかし、繰り返し発症したり、少しずつ大きくなったりして悩んでいる方もいるでしょう。
そこでこのページでは、粉瘤ができやすい人の特徴や粉瘤と似ている症状、予防法や高須クリニックでの治療法を医師の立場から解説いたします。
粉瘤についてわからないことやお悩みの方は参考にしてみてください。
目次
粉瘤(アテローム)は皮膚に出来る良性腫瘍
粉瘤は、皮膚の下に袋状にできる良性腫瘍のことで、「アテローム」とも呼ばれます。
腫瘍といっても、癌のような悪性のものではなく、あくまで良性腫瘍のため、大きな心配はいりません。
粉瘤の中には、垢や皮脂などの老廃物が溜まっており、大きさは直径数mm~数cm程度と人によってさまざまです。
通常は痛みなども感じず、無症状で過ごすことができますが、袋が破れたり細菌などに感染すると、腫れや痛みをともなうことがあります。
粉瘤が出来やすい人とは?
粉瘤は、年齢・性別を問わず誰でも発症します。
粉瘤は、本来ターンオーバーで剥がれるはずの皮脂や垢がなんらかの理由でとどまってしまうことが原因といわれていますが、現在でも詳しいことがわかっておらず、特に誰ができやすいかはっきりとしたデータも見つかっていません。
ただし、傾向的にピアス跡やニキビ跡、わきがの手術跡などの外傷部分がある人は、粉瘤ができやすいといえます。
こういった部分には垢や皮脂などの老廃物が溜まって塊となりやすいためです。
同じように汗をかきやすい人、体内のホルモンバランスに乱れがある人も、粉瘤ができやすいといわれていますが、常に清潔にしていても発生することがあり、必ずというわけでありません。
性別でいえば、女性よりも男性のほうができやすく、さらには先天的な体質によっても粉瘤ができやすい人もいます。
粉瘤ができやすい部位
粉瘤は、顔や体のさまざまな部位に発症する特徴があり、特定の場所だけに出現するものではありません。
特に出来やすいとされているのが、頭部・眉・頬・首・耳周り・背中などです。
粉瘤と間違いやすい症状
粉瘤と似ている皮膚疾患には、次のようなものがあり、それぞれの症状と見分け方をご紹介します。
ニキビ
ニキビは、過剰な皮脂分泌の増加やアクネ菌の増殖、毛穴の詰まりなどによって発生します。
ただし、ニキビは粉瘤のように皮膚の下ではなく、毛穴に起こるため、時間の経過で大きくなることはなく、またニオイがない特徴があります。
脂肪腫
脂肪腫は粉瘤と同じ良性腫瘍の一種ですが、皮膚の下でゴロゴロと動く特徴があります。
粉瘤の場合は、皮膚と癒着しているため、動かすと一緒に粉瘤も動きますが、脂肪腫は皮膚に癒着していないため、皮膚と連動せずに塊が動きます。
せつ(おでき)
せつは、細菌感染症の一種で、発症すると膿ができ、腫れや痛み、発熱などが起こることが特徴です。
膿がしこりのようになるため、最初は粉瘤と間違いやすそうですが、粉瘤との違いとして、痛みや発熱などが起こりやすいため、見分けることができます。
ガングリオン
ガングリオンは、ゼリー状のしこりができる粉瘤と同じ良性腫瘍の一種です。
関節の周囲にできることが多く、大きさもさまざまで、痛みはないこともあれば、神経に近いとしびれや痛みが起こることもあります。
見た目で粉瘤との違いを見極めるのは難しく、関節の周辺に起こることが多いですが、ご自身でわからない場合は専門医への受診がおすすめです。
化膿性汗腺炎
化膿性汗腺炎は、汗を分泌する汗腺に細菌が繁殖する感染症です。
汗が溜まりやすい脇の下や陰部、乳房の下などに膿がたまり、進行すると痛みや腫れも起こることがあります。
粉瘤との違いは、痛みや腫れがあること、また、押して膿を出すと黄色になっていることが特徴です。
粉瘤であることの見分け方
このように、症状によって粉瘤とはいくつかの違いがありますが、粉瘤とほかの皮膚疾患を見分けるおもなポイントは、次のとおりです。
- 一定期間様子を見ても治らない
- 治ったと思っても再発する
- 初期段階では腫れや痛みなどの症状がない
また、粉瘤は少しずつ大きくなったり、腫瘍の中央に黒い毛穴が見られたりすることも特徴となっています。
いずれにせよ、ご自身ですぐ粉瘤であることを見分けることは難しく、時間をかけて状態を観察する必要があります。
粉瘤の予防方法
粉瘤は発生原因が明確でないため、自分でできる確実な予防方法はありません。
体質によっても左右されますが、肌の状態を良好に保つ生活を心がけることは大切です。
具体的には、次のようなことに気をつけてセルフケアをおこないましょう。
- 肌を常に清潔に保つ
- 丁寧なスキンケアを継続する
- 肌に刺激を与えないようにする
- 十分な睡眠時間を確保する
- バランスの取れた食生活にする
肌の状態を良好に保てれば、ニキビやニキビ跡がきっかけとなる粉瘤(アテローム)も予防しやすいでしょう。
粉瘤(アテローム)は自分で治せる?

粉瘤は、皮膚の中にある袋状の構造物を取り除かない限り、完治はしません。
自分で粉瘤を潰しても治ることはなく、仮に治ったように見えたとしてもまた発生してしまうでしょう。
また、自分で粉瘤を潰したりしようとすると、刺激によってさらに大きくなったり、細菌による感染などを起こして腫れや痛みを引き起こしたりするおそれがあります。
悪化してからクリニックで治療すると、傷跡が大きくなってしまうことが懸念されるため、粉瘤の潰したりするなどのことは控えておきましょう。
クリニックで早めに粉瘤を切除するメリット
粉瘤は治療を必要とするものではありませんが、放置すると大きく膨らんでくる可能性や、溜まった老廃物が臭うようになる可能性があります。
また、初期段階の粉瘤は肌色や白色ですが、悪化すると黄色・黒色・青色などに変わり目立つケースもあるでしょう。
そのため、粉瘤が気になる場合は、早めに専門医の診察を受けることが大切です。
粉瘤がまだ小さいうちに切除すれば、傷跡が小さく済み、細菌感染による腫れや痛みに悩むこともないでしょう。
粉瘤のクリニックでの切除方法
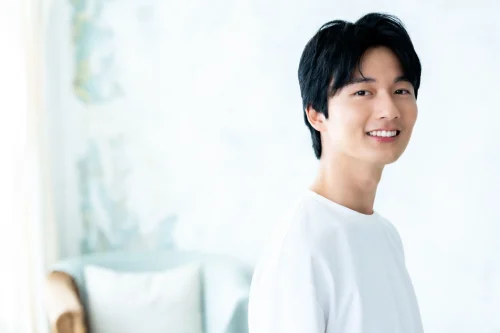
粉瘤のクリニックでの治療法には、大きく分けて「くり抜き法」と「切開法」との2種類があります。
「くり抜き法」
くり抜き法は、特殊な器具を使って、粉瘤のできた皮膚をくり抜いて、溜まった老廃物を取り出す方法です。
小さな穴から抜き出すため、傷跡を小さくしやすいメリットがあるものの、粉瘤のある袋を取り残してしまうなど、再発の可能性が高いため、高須クリニックでは実施しておりません。
「切開法」
メスを使って粉瘤のある皮膚を切除し、下にある袋をすべて取り出し切除する方法で高須クリニックで実施している方法です。
一般的には傷跡が残りやすいデメリットがあると言われていますが、高須クリニックでは、切開法でも傷跡が目立ちにくいよう、最小の切開を行い、さらに皮膚のしわに沿って1本の線になるように丁寧に縫い合わせるため、実際にはそれほど目立ちません。
また、局所麻酔とクリーム麻酔による痛みの少ない施術をするほか、腫れを早く引かせる漢方薬「治打撲一方(ヂダボクイッポウ)」を常備しているため、安心して施術を受けられます。
高須クリニックでは丁寧にカウンセリングを行い、患者様が十分に納得してから治療を開始します。ご不明な点があれば何でもご質問ください。
【粉瘤の切除】施術の流れ・料金・注意事項
ここでは、高須クリニックでの粉瘤(アテローム)の切除について、施術の流れ・料金・注意事項を紹介します。
施術の流れ
粉瘤(アテローム)の切除にかかる時間は10~60分程度で、日帰りで出来る比較的簡単な手術です。一度に複数箇所の粉瘤(アテローム)を切除することも可能ですが、それぞれの粉瘤(アテローム)の大きさや位置、患者様の負担などをふまえ、最適な治療計画を提案します。
粉瘤(アテローム)の具体的な切除の流れは、次のとおりです。
- 麻酔
粉瘤(アテローム)のある部分に局所麻酔注射をします。必要に応じて、クリーム麻酔を塗布することもあります。 - 粉瘤(アテローム)の切除
粉瘤(アテローム)の大きさに合わせて最小の範囲で切開し、根本から袋ごと除去します。 - 縫合
切開した部分を、傷口が残りにくいように縫い合わせます。なお、縫い合わせた部分が濡れなければ、当日からシャワーも可能です。 - 抜糸
切除から約1週間後に抜糸します。これで粉瘤(アテローム)の治療は終了です。
料金
高須クリニックにおける粉瘤(アテローム)の切除の料金は、次のとおりです。
- 55,000~165,000円(税込)【銀座高須クリニック、横浜、名古屋、大阪】
※最新の価格は、施術ページをご確認ください。
施術料金は、おもに粉瘤(アテローム)の大きさによって決定します。その他、炎症の程度や施術部位によって料金が異なる場合があります。
注意事項
個人差はあるものの、粉瘤(アテローム)を切除すると、1週間程度は軽い腫れが見られます。
また、基本的には一度袋を取り除けば再発の心配はありませんが、きれいに取り切れない場合は再治療が必要になるかもしれません。
さらに体質によっては、切除した箇所で粉瘤(アテローム)が再発することがあります。
繰り返す粉瘤(アテローム)の悩みを解消するなら高須クリニックへ
粉瘤は、誰でも発症し得る良性の腫瘍です。粉瘤を予防するためには、肌の状態を良好に保つ生活を心がけることも大切ですが、体質によっては肌の状態に関係なく粉瘤が出来やすい人もいるでしょう。
粉瘤が気になる場合や、悪化による目立ちやすさを心配する方には、クリニックでの早めの治療がおすすめです。
高須クリニックの施術は、粉瘤の切除後に丁寧に縫い合わせるため、傷跡が目立ちにくいのが特徴です。
また、麻酔による痛みの少ない施術・腫れを早く引かせる漢方薬の常備により、安心して施術を受けられる体制を整えていますので、ぜひ一度ご相談ください。
美容外科はもちろんのこと、形成外科専門医としての経歴も長く、技術には自信があります。
なかでも、二重まぶたの手術や鼻の手術が得意です。
患者様が最善の方法を見つけ、納得のいく結果を手に入れられるよう、全力でサポートさせていただきます。
術後の修正にも最後まで責任を持って対応いたしますので、安心してご相談ください。
この記事に関連する施術

当サイトは高須クリニック在籍医師の監修のもとで掲載しております。


高須クリニックには、日本美容外科学会(JSAS)や国際美容外科学会で学会長を務めた院長をはじめ、日本形成外科学会専門医を持つ医師が数多く在籍しております。
また、日本美容外科学会(JSAS)専門医、医学博士、日本美容外科医師会会員、日本美容外科学会会員、日本美容外科学会(JSAPS)専門医、日本美容外科学会会員(JSAPS)、日本美容外科学会会員(JSAS)、臨床研修指導医、日本麻酔科学会指導医、日本麻酔科学会専門医、麻酔科標榜医、日本脂肪吸引学会会員、日本肥満学会会員、臨床皮膚科学会会員、日本美容皮膚科学会員、日本皮膚科学会専門医、日本美容皮膚科学会会員、日本レーザー医学会会員、BOTOXVISTA認定医、サーマクールCPT認定医、ジュビダームビスタ認定医、VASERLIPO認定医、ミラドライ認定医、日本歯科学会会員、国際インプラント学会インプラント認定医、歯学博士、日本眼科手術学会会員など様々な科目の専門医や資格を保有した医師が在籍しています。