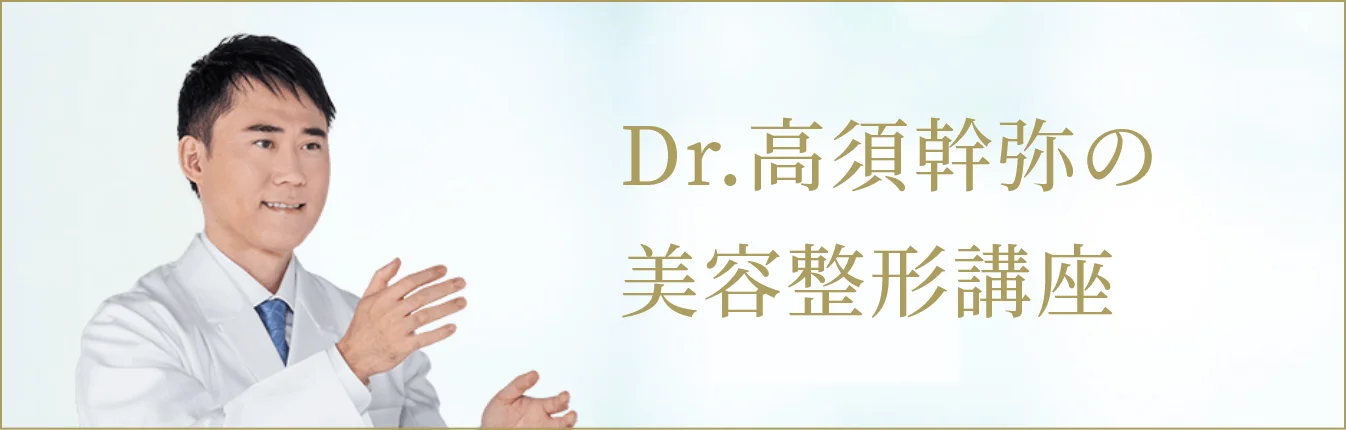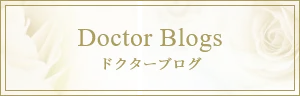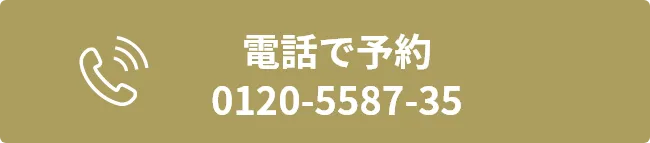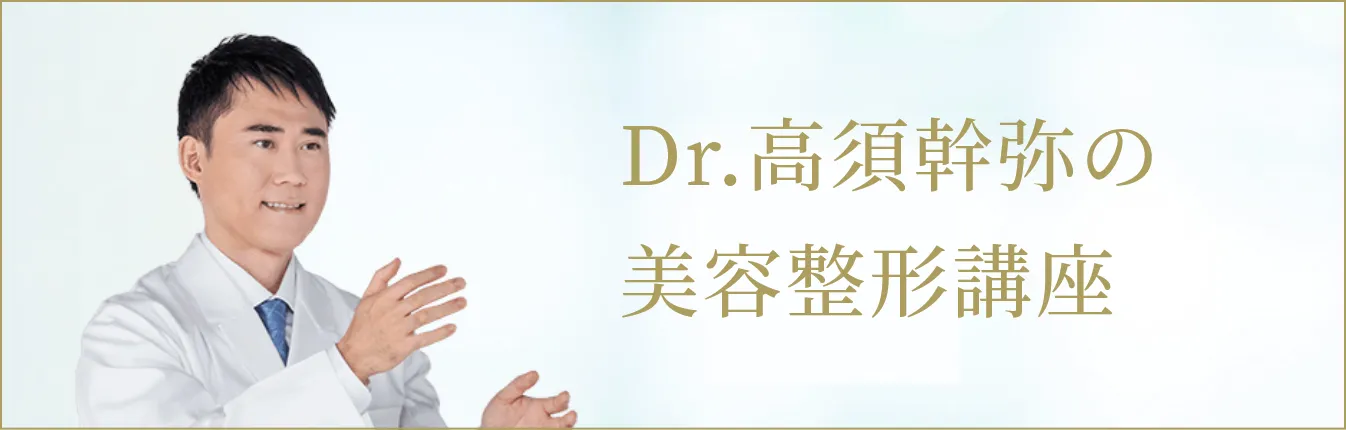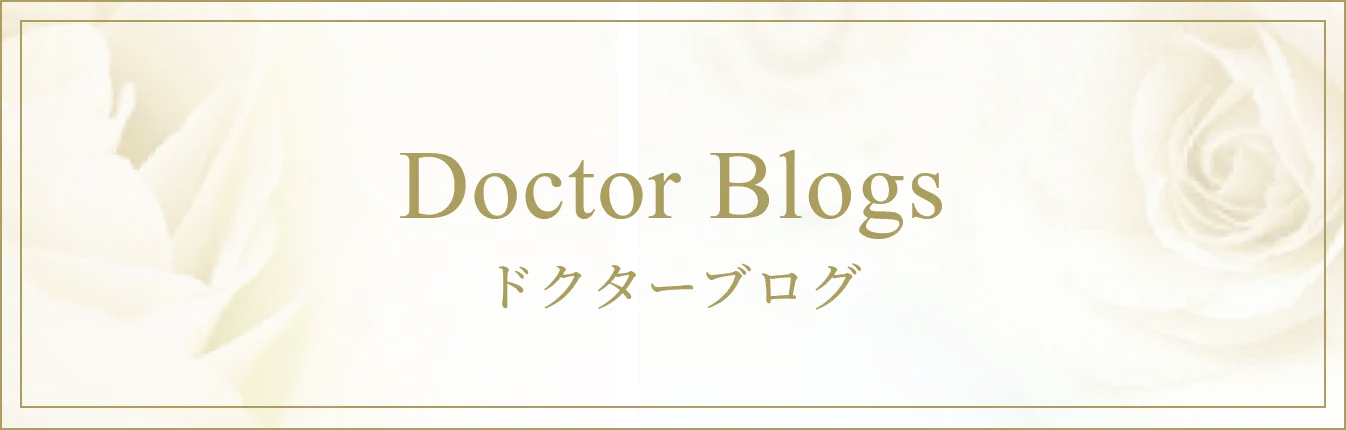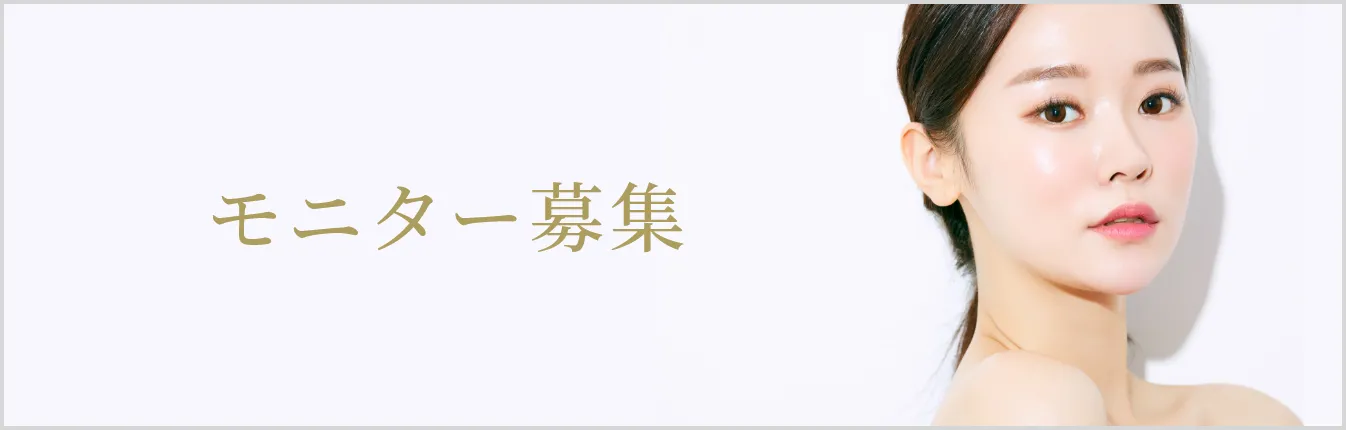- 高須クリニックホーム
- yes! 高須ビューティーナビ
- ビューティナビ記事一覧
- しみ・そばかす
- 美容皮膚科医が教える自力でそばかすを薄くする方法や予防のポイントは?
美容皮膚科医が教える自力でそばかすを薄くする方法や予防のポイントは?

2024.09.10
読了目安:この記事は約 13 分で読むことができます。
そばかすは、しみの一種で、鼻や頬を中心としておもに顔に広がる小さな斑点です。
「幼い頃からそばかすがある」という方もいれば、「年齢とともに顔のそばかすが濃く目立ってきた」方もいるのではないでしょうか?
そばかすを薄くする方法は、いろいろな方法が紹介されていますが、数も多く、よくわからない方法を試して症状が悪化してしまった方も少なくありません。
そこでこのページでは、そばかすの治療に長年携わってきた美容皮膚科医・高須英津子の立場でおすすめできるそばかすを薄くするセルフケアの方法から、美容皮膚科での治療までを厳選してご紹介します。
いまあるそばかすを薄くする方法から今後発生させないために日常生活で予防する方法までご紹介しているので、気になる方はぜひご覧ください。
目次
そばかすは数あるしみの一種類
そばかすは、鼻や頬を中心としておもに顔に広がる小さな斑点ですが、医学的には「雀卵斑(じゃくらんはん)」と呼ばれ、しみの種類の一つとされています。
しみには、老人性色素斑(日光黒子)、肝斑、炎症後色素沈着といった種類があり、特にそばかすと肝斑は間違いやすいしみの一つです。
肝斑は点状に見られるそばかすとは違い、雲がかかったように薄いしみが顔全体に広がるのが特徴で、その原因も後述するそばかすとは違って30~40代の女性の女性ホルモンの乱れによって発生しやすく、原因から異なっています。
また、そばかすは肝斑と違い、顔だけでなく、肩・胸元・腕・背中などにできる場合もあります。
自分のしみがそばかすなのか、肝斑なのかよくわからない場合もあり、中には肝斑とそばかすが同時に発生しているケースもあります。
今後ケアをするのであれば、まず皮膚科やクリニックでの診察でしみの種類について特定することもおすすめです。
そばかすになる原因は?

そばかすになる原因は、本来、遺伝的な要因でできるものをさしており、家族にそばかすのある方がいる場合はそばかすができやすい傾向があります。
個人差はあるものの、遺伝性のそばかすは5~6歳頃からでき始め、思春期頃にかけて発生しやすくなります。
年齢とともに色が濃くなったり、数が増えたりするのが特徴です。
メラニン色素の過度な沈着でそばかすが目立つことも
ただし、最近では強くなっている紫外線の影響や肌への過剰な刺激に、濃い色素を持つメラニンが過剰に生成され、排出されにくくなり、肌にそのまま沈着することで、子供の頃に目立たなくても大人になってから急にそばかすが目立つようになることがあります。
同じように、色白の方や、髪色が明るい方もメラニンの影響によって、肌色に比べてそばかすが悪化しやすい傾向があります。
美容皮膚科では、遺伝以外の要因も含めてそばかすの治療を行う患者様が多くなっています。
そばかすを悪化させない、予防するための自力でできる方法

まず美容皮膚科医として最初にお伝えしたいのは、セルフケアだけでそばかすを消したり、薄くすることは難しいものです。
そばかすの症状は患者様によって程度や、体質の問題、さらには肝斑などと混在など、個人差がかなりあり、自己判断だけでそばかすを消すことはあまり期待できません。
しかし、そばかすの悪化を防いだり、今よりも薄くする、予防するといったことは適切なセルフケアを時間をかけて続けることによって改善の可能性はあります。
大人の方からお子様まで、そばかすを悪化・再発させないための普段の生活のなかでも気を付けるべき3つの方法をご紹介します。
紫外線対策を徹底する
しみのもととなるメラニンは、紫外線を浴びることで活性化します。そのため、そばかすは紫外線の影響で濃くなりやすいでしょう。
そばかすを悪化・再発させないためには、季節を問わず、日頃から紫外線対策をすることが大切です。
室内で過ごしていても、普通の窓ガラスだと7割程度は紫外線を通すため、気付かないうちに紫外線を浴びてしまうかもしれません。
室内でも日焼け止めを塗るようにし、外では日傘や帽子なども併せて活用するとよいでしょう。
後ほどご紹介する美容医療の施術を受ける場合は、ダウンタイム中に紫外線対策をしっかりできるかどうかによっても、治療の選択肢が変わるほど紫外線対策は重要なものです。
バランスの良い食事を摂る
必要な栄養素をバランス良く摂れていないと、肌のターンオーバーが乱れ、メラニンが排出されにくくなります。
バランスの良い食事を基本とし、L-システインやビタミンCのほか、ビタミンEの摂取を意識するのがおすすめです。
これらの成分は、メラニンの生成を抑制したり、ターンオーバーをサポートしたりしてくれます。
食事だけの摂取が難しい方は次にご紹介するサプリメントによって補給することも向いています。
肌への刺激は最小限にする
肌は、「ゴシゴシと洗う」「タオルで擦るように拭く」などの物理的な刺激を受けると、肌を守るためにメラニンを生成してしまいます。
そばかすを悪化・再発させないためには、スキンケアやメイクの際などに、肌に刺激を与えないようにすることも大切です。
また、肌に合わない化粧品を使うことや、毎日長時間メイクしたまま過ごすことも、肌への刺激となるため注意しましょう。
サプリメントや市販外用薬を使って自力でそばかすを薄くする方法
普段のセルフケアとあわせてそばかすを薄くしていくには、サプリメント、外用薬(市販化粧品)を使う方法があります。
ただし、これだけで実際に得られる効果には個人差が大きく、あまり過度な期待はできません。また、即効性もないため、時間をかけて取り組む必要もあります。
非常にたくさんの商品が発売されていることもあり、ここではそばかすを薄くするための効果的な成分についてご紹介するので、選び方の参考にしてみてください。
サプリメント
そばかすに効果がある成分を含んだ内服薬により、体の内側からアプローチする方法があります。内服薬として用いられる代表的な成分には、次のようなものがあります。
- L-システイン:メラニンの生成を抑制する働きや、メラニンの排出をサポートする働きがある
- ビタミンC:できてしまったメラニンを薄くする働きがある
- トラネキサム酸:メラニンの生成を抑制する働きがある
外用薬
そばかすに効果がある成分を含んだ外用薬により、体の外側からアプローチする方法もあります。
ただし、最初にご紹介した通り、しみにはいろいろな種類があり、判断を誤って自分で選んだ外用薬を使ってしまうと、逆に症状が悪化してしまうケースもあります。
できればケアを始める前に皮膚科やクリニックの診察でしみの種類を特定してもらうことはもちろん、どのような外用薬が向いているのか、医師の所見やアドバイスを受けることをおすすめします。
外用薬として用いられる代表的な成分は、次のとおりです。
トレチノイン(レチノイン酸)
トレチノインとは、ビタミンAの誘導体で、メラニンの排出をサポートする働きや、肌のターンオーバーを促進する働きがあり、時間をかけて使うことにより、そばかすへの効果が期待できます。
ただし、ビタミンAは、脂溶性ビタミンのため、過剰摂取による健康への影響も指摘され、特に妊娠中や授乳中、妊娠予定のある方は使用を控えるようにしましょう。
ハイドロキノン
ハイドロキノンは、強力な美白成分で、市販の化粧品にもよく配合されています。
メラニンの生成を抑制する働きや、メラニンが生成される元となる「メラノサイト」自体を減らす効果があるとされています。
強い美白効果がある反面、取り扱いには注意が必要で、使用中に紫外線を浴びることで逆にそばかすが濃くなったり、肌質によっては炎症などの副作用が起こることもあります。
ハイドロキノンの濃度によっても効果が変わるため、市販品を自己判断で使うよりも医師の診察に基づいて処方されるお薬のほうがより安心して使えると言えるでしょう。
美容医療でそばかすを消したり薄くする方法
そばかすを消したり、より確実に薄くするには、美容医療の施術を受けるのがおすすめです。
そばかすやしみに関する施術は非常に多くあり、高須クリニックでは、症状の程度や、肌質、しみの種類などを的確に判断し、丁寧なカウンセリングで、患者様のお悩みや希望を伺いながら最適な施術をご提案しています。
患者様のご要望として多いのがダウンタイムについてです。
まずはダウンタイムなしで気軽に受けたい場合と、ダウンタイムありで1回の施術で終わる施術についてご紹介します。
ダウンタイムなしで気軽に受けたい場合におすすめの施術
腫れなどがなく、ダウンタイムをできるだけ少なくしてそばかすを消したり、薄くしたい場合は、IPL(フォトフェイシャルM22)をおすすめします。
IPL(フォトフェイシャルM22)は、メラニンや毛細血管などのトラブル部分にだけ反応する光を照射して、しみ、そばかすなどを総合的にケアできる施術で、1回につき20~30分で終了し。ダウンタイムはありません。
そばかすの施術の場合、3週間に一度、3~6回ほど継続的にうけることで、確実に効果実感が得られるケースが多くなっています。
一回で施術を終わらせるおすすめの施術
通院回数を減らして一回で施術を終わらせたい場合なら、ピコレーザー(PicoWay)をおすすめします。
ピコレーザー(PicoWay)とは、ピコ秒(1兆分の1秒)パルスで照射を行うレーザーのことで、肌に沈着したメラニン色素などを破壊し、主にしみやそばかすの除去が期待できる治療です。
従来型のレーザー治療に比べ、施術時の痛みやダウンタイムが少なく、そばかすの場合、一回の施術で効果を期待できる場合が多い施術です。
Qスイッチ・アレキサンドライトレーザー(アレックストライバンテージ)も最新型のレーザー治療の一種で、そばかすはもちろん、肝斑・くすみといった状態にも対応できる施術です。
複数のしみが顔に散在している場合にオススメの施術法です。
複数のしみが混在している場合でも適切な治療を
最初にもご紹介した通り、顔のしみは必ずしもそばかすだけではなく、肝斑などの他のしみも発生している場合があります。
しみと肝斑では、根本的に原因も異なり、そばかすだけの治療を行っても肝斑のしみは残ったままになることもあり、結果的に失敗と感じることが少なくありません。
高須クリニックでは、単に施術を行うだけではなく、患者様のしみの原因が何であるかをしっかりと特定することで、患者様にとって後悔のない最適な施術をご提案することができます。
高須クリニックでは次のような多数の施術をご用意しており、患者様の症状やお悩みに合わせて最適な施術をご提案することができます。
【機器を使う施術】
- IPL(フォトフェイシャルM22)
- シミ・あざ取りレーザー
- ピコレーザー(PicoWay)
- Qスイッチ・アレキサンドライトレーザー(アレックストライバンテージ)
【薬品を使う施術】
- トレチノイン・ハイドロキノン
- イオン導入
- グロースファクター(成長因子)
【針・糸を使う施術】
- イタリアンリフトファイン
【注射・点滴を使う施術】
- しみ・くすみ対策点滴(ビタミンC点滴)
- 白玉注射(グルタチオン)
そばかすの悩みを解決するなら高須クリニックへ
幼い頃からそばかすがあるという方でも、美容医療によってそばかすを薄くし、明るくきれいな肌を目指せます。
ただし、そばかすを悪化・再発させないためにも、紫外線対策を徹底すること・バランスの良い食事を摂ること・肌になるべく刺激を与えないことは、日頃から心がけましょう。
高須クリニックでは、患者様の症状と希望に応じて、最適な治療をご提案します。
美容皮膚科を専門として、皆さまの「美肌づくり」のお手伝いができれば・・・と常々思っています。
しみ、そばかすをはじめ、赤ら顔やニキビ、ニキビ跡、小じわ、たるみなど、お肌に関するお悩みは、お気軽にご相談ください。女性の立場から、キメ細やかな治療を心がけています。
しみ・そばかすではこんな記事も読まれています
この記事に関連する施術

当サイトは高須クリニック在籍医師の監修のもとで掲載しております。


高須クリニックには、日本美容外科学会(JSAS)や国際美容外科学会で学会長を務めた院長をはじめ、日本形成外科学会専門医を持つ医師が数多く在籍しております。
また、日本美容外科学会(JSAS)専門医、医学博士、日本美容外科医師会会員、日本美容外科学会会員、日本美容外科学会(JSAPS)専門医、日本美容外科学会会員(JSAPS)、日本美容外科学会会員(JSAS)、臨床研修指導医、日本麻酔科学会指導医、日本麻酔科学会専門医、麻酔科標榜医、日本脂肪吸引学会会員、日本肥満学会会員、臨床皮膚科学会会員、日本美容皮膚科学会員、日本皮膚科学会専門医、日本美容皮膚科学会会員、日本レーザー医学会会員、BOTOXVISTA認定医、サーマクールCPT認定医、ジュビダームビスタ認定医、VASERLIPO認定医、ミラドライ認定医、日本歯科学会会員、国際インプラント学会インプラント認定医、歯学博士、日本眼科手術学会会員など様々な科目の専門医や資格を保有した医師が在籍しています。